先日、ツイッターで「プロ驚き屋」(または「驚き屋」)という今年生まれたばかりの超ニッチなスラングの意味を英語で紹介したところ、想定外に結構反響があったので(以下ツイート)、この記事でその意味や英訳を解説しようと思います。
プロ驚き屋 (“a professional surprised man”, New Slang)
= a person who excitedly shares state-of-the-art tools/technologies like ChatGPT on social media with hyperbole like 神/最強/ヤバすぎ, as well as with hallucination/overstatement at times based on a few cherry-picked examples— Takashi’s Japanese Dictionary (Takashionary) (@takashionary) April 10, 2023
(個人的には研究者・エンジニア界隈の日本人に向けた冗談のつもりで書いたので、たくさんの外国人の方にウケて結構びっくりしました。反響の大きさやコメント等を見ると、「プロ驚き屋」が世界中で蔓延っていることがわかりますね。。。笑)
「プロ驚き屋」・「驚き屋」の意味
上記のツイートでは、「プロ驚き屋」の意味を以下のように表現しました。
a person who excitedly shares state-of-the-art tools/technologies like ChatGPT on social media with hyperbole like 神/最強/ヤバすぎ, as well as with hallucination/overstatement at times based on a few cherry-picked examples
— Takashi’s Japanese Dictionary (Takashionary) (@takashionary)
ざっくり日本語に言い換えると
「SNSでChatGPTなどの最先端ツールやテクノロジーを、神・最強・ヤバすぎ、のような誇張表現を使って興奮気味に紹介し、時折それを自分にとって都合の良いように選んだ2、3個の成功例に基づいて、妄想や行き過ぎた主張を交えながら行う人」
となります笑。英語に興味がある人向けに少しだけ解説すると、“state-of-the-art” とは 「最新の、最先端の」という意味の熟語で、AI系の論文で多用される表現です(頭文字を取ってSOTAとよく言われます)。また、“hyperbole” (発音はハイパーボリ, haɪpɜːbəli)は「(広告などでみられるような)誇張、大袈裟な表現」という意味で、 “exaggeration” 「誇張」やこの後に使った“overstatement” 「行き過ぎた・盛った主張」の類義語です。また、“hallucination” は本来「幻覚、妄想」という意味ですが、最近では「AIが自信満々に出力する嘘(事実とは異なる内容)」を指す専門用語として使われており、ここではある種の皮肉として使っています。また、最後の “cherry-pick” と言う単語もAIの研究分野で頻出な単語で、直訳は「 サクランボを摘む」ですが意味は「(新鮮なサクランボだけを選んで摘むように)数ある例の中から自分にとって都合の良い物を選ぶ」です。例えば、何かのタスクをChatGPTで解こうとして色々試行錯誤した後、上手くいった時の例だけをピックアップして紹介したとしたら、それはまさに典型的な”cherry-picking” な行為と言えます。
見ての通り、AI研究者にとって馴染みの深い単語をあえて多用した内輪ネタに近い内容だったので、反響が大きくて驚きました。ちなみに、「プロ驚き屋」の直訳は “a professional surprised man” としましたが、”a professional amazed man” や “freak-out specialist” とかでも良かったかなと思います 。また、「驚き屋」のように今までに存在しなかった新語を英語で新しく作るとしたら、”tech stokedman” (stoked 「超興奮した」+ man)” や “dumbstrucker” (dumbstruck 「驚きのあまり唖然とした」+ er) みたいな感じになるかもしれません。
「プロ驚き屋」の例・使われ方
TwitterなどのSNSで
- 「これはヤバすぎる」、「神ツール」、「最強のAIが誕生」といった誇張表現を羅列
- 「これで医者/弁護士/プログラマーはもう必要なくなる」のような極端な未来予想を展開
- 新しいツールや論文の要点らしき物を体言止めの箇条書きで紹介
しているツイートを見たら、多分それは「プロ驚き屋」の投稿です。そのような投稿がTwitterで最近急増しているのを受けて、AI研究者やエンジニア、プログラマーなどが「よく見たら機械学習の研究者や専門家ではなく、ただのプロ驚き屋だった」のように皮肉的に使っています。もし今後この単語がネットスラングとして定着した場合、「プロ驚き屋」は少し言いにくいので「プロ驚」とか「驚き屋」、「プロサプ」のような略語が使われだすかもしれません。
類義語
プロ煽り屋 、自称研究者、ミーハー、意識高い系、アフィカス、いかがでしたかブロガー
「プロ驚き屋」の英訳
引用リツイート等で「英語でもこういう単語を今すぐ作るべきだ」というコメントが外国人の方から沢山あったので、完全に同じ意味の英単語は(まだ)なさそうです。ただ、いわゆる「プロ驚き屋」を言及するのに以下のような英単語が使われているようです。
techbro
この単語がコメントの中で一番多かったです。「ついに “techbro” の日本語が生まれた」と言う人も数人いました。tech (technologyの略) + bro (brother の略で “man” のような意味)から出来た単語で、ネガティブなニュアンス(隠キャっぽい)を持つ単語です。日本語で言うと「IT野郎」、「ITオタク/マニア/ニキ」、「IT通()」等に近いかもしれません。より具体的に、“AI bro” 「AI通()」とか “crypto bro” 「仮想通貨ニキ」のように言うこともあります。
bullsh*t artist
bullsh*t は「嘘、デタラメ」という意味の汚めなスラングで、それのartist (アーティスト)なので「デタラメ屋」みたいなニュアンスです。何かそれっぽいことを言って情報商材を巧みに売りつけるような人を表すのに使います。 これに似た単語に “con artist” 「詐欺師」というのがあり、こちらはもっと一般的な単語です。また、snake oil salesman (蛇の油営業マン)という有名なイディオムもあり、これは「価値のない物を売りつけて儲ける人」という意味です(snake oil で「インチキ」という意味になります。以前、「直訳すると変な英語の表現・慣用句一覧」というブログ記事で紹介しました)。
hype man
hype とは「(メディアなどによる)誇大宣伝」という意味で、今のAIブームを表すのにピッタリの単語です(なので、僕もこの単語をツイートで使うことを最初は考えていました)。例えば、驚き屋のツイートは “AI hype tweet” のように表すこともできます。
そして、hype man とは元々「(ラップ音楽などで)メインボーカルの後ろでシャウトしながら踊ったり歌ったりして、観客を盛り上げる人」を表す単語なのですが、もっと広い文脈で「何かを促進したり盛り上げようとする人」や「盛り上げ隊長」みたいな意味でも使われます。ただ、hype と違って必ずしもネガティブな単語ではなく、例えばこのWBC2023の公式ツイートでは、ヌートバー選手が円陣を組んで他の日本人選手の士気を高めている様子を “hype man” と表現しています。
他にはややマイナーな単語になるのですが、hype-monger という単語もあり、こちらは「何かを誇大宣伝する人」という意味になります。mongerとは「商人、〇〇屋」または「くだらないものを促進する人」という意味で、”fish-monger”(魚屋) や “gossip-monger” (ゴシップ屋、ゴシップ好き) 、scare-monger (人々の不安を徒に煽る人やメディア) のように他の単語とよく組み合わさって使われます。個人的には、hype man よりこちらの方が「プロ驚き屋」のニュアンスと近い気がします。また、”hypebeast” (hype + beast「獣」)という単語もあり、「(注目を集めるために)最新の流行(特にファッション)を熱心に追う人」を表すのに使われます。
shill
shill は「サクラ、偽客」という意味で、例えば “crypto shill” は「(お金儲けのために)仮想通貨を誇大に持ち上げてして人を釣る人」という意味でよく使われます。そのため、 お金目的のプロ驚アカウントに限れば “AI shill” や “tech shill” 等と言えば恐らく伝わります。ちなみに、“shiller” と言うこともあります。
語源
Twitterでこの単語が(AIに関する文脈で)使われ出したのは、2023年3月16日に公開されたこのnoteの記事における以下の文がキッカケになったようです。
結局のところ、「何に使うか」ということが一番大切という視点を持たないと、ただただ「プロ驚き屋」の過剰な驚愕表現に振り回されることになってしまう。
実は「プロ驚き屋」という言葉自体は2015年のTwitter で一度だけ使われていることが確認できるのですが、上で説明した意味の語源はこの記事である可能性が高いです(ただし、この記事よりも前にどこかで使われた可能性を完全には否定できません)。
そして、この記事の約10日後に投稿された以下のツイートもこの言葉の拡散に大きく貢献したようです。
「〜がヤバい」みたいなAI系のツイートはプロ驚き屋だったりして、ソースコード見たり、中身ちゃんと使ってない気がしているw
— GOROman@NAMM SHOW行きます (@GOROman) March 27, 2023
関連記事
- 体の一部を使った英語の誇張表現 (“jaw-dropping” など)

- その他英語の大袈裟な表現 (“crystal clear” 、”brand new” など)

- 「プロ驚き屋」の意味を英語で紹介

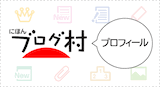








コメント
コメント一覧 (3)
[…] 「プロ驚き屋」の意味と英訳 […]
[…] 「プロ驚き屋」の意味と英訳(2023年 新語ネットスラング) […]
[…] 「プロ驚き屋」の意味と英訳(2023年 新語ネットスラング) […]